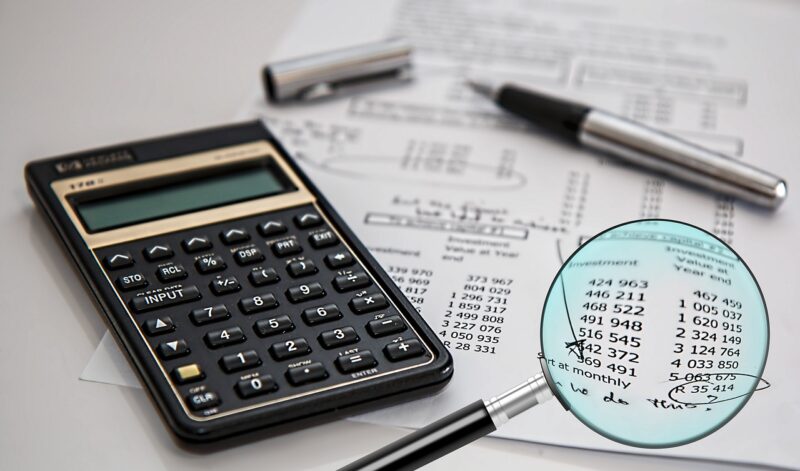固定資産税(土地)の交渉#1 失敗談+アイデア募集
5月といえば、固定資産税の納付書が送られてくる時期です。
(早ければ4月の自治体もあります)
- 固定資産税といえば、賃貸マンションや太陽光発電ではほぼ唯一の原価
- 類似の償却資産税(設備)なら自己申告だから、計算根拠(=自分)が明確
- でも固定資産税(土地+建物)になると自治体からの言い値で計算がよくわからん
ちょっとでも安くならんかな、、、こんな悩みで一歩踏み出てみました。
本日の記事
- 固定資産税とは
- 周囲の成功体験談
- なぎささんの交渉ネタ
- 交渉結果とそこからの学び
この記事からわかること
(成功したわけではないですが)素人でもできる交渉ネタとその結果を教えます。
人によっては交渉がうまくいき、過去の支払い分も含めて、過払金の取り返しに成功しているようです。また、固定資産税(市税)は不動産取得税(県税)と同じ評価方法を使っています。市税での節税交渉がそのまま県税の過払い認定につながる可能性があるので、2重、3重にメリットがあります。
私はまだ成功していませんが、トライアンドエラーを考えるきっかけになればと思います。
この記事を書いているなぎささんは
宮崎県と兵庫県に1機ずつ(計2機)太陽光発電所を経営しています。
先日兵庫県###市から固定資産税の納付書が届き、高いと感じたので、問い合わせてみました。
結果、減額交渉は失敗に終わりましたが、課題も見つけたので、勉強してみようと思います。
まずは、次につなげるためにも、今回のトライアンドエラーを共有します。
1.固定資産税とは
素人ながらも、簡単に解説します。
✔︎固定資産税とは市税です
税金には、大きく分けて4分類があります。
国税、県税、市税、関税。
この4項目の中で見ると、固定資産税は市税になります。
どこの市区町村も市役所の中に課税課という部署があり、各市区町村が独自に計算しています。もちろん計算方法は全国一律ですが、計算する人やシステムは独自です。当然ながら、市区町村によっては対応の違いが生じます。同じことをやっても、成功する人と失敗する人がいるのにはこういった理由もあると思います。
✔︎固定資産税の課税対象は土地と建物です
「固定資産」とは1件20万円以上し、1年間以上使用できるものを指します。
大きく分けて次の7項目があり、姿形を変えて、「資産課税」をされます。「固定資産税」というとき、広い意味ではこの7件全てを指しますが、狭い意味でいうと土地に固定されたものだけになります。
- 土地 固定資産税
- 建物 固定資産税
- 建物付属設備 固定資産税
- 構築物 固定資産税
- 設備 償却資産税
- 車両 (軽)自動車税
- 器具備品 償却資産税
✔︎償却資産税との違いは評価方法です
固定資産税と一緒に納税する似て非なるものとして、償却資産税というものがあります。
両者の違いは、申告義務と評価(計算)方法の有無です。
償却資産税は所有者が税務申告の義務を負います。市役所はその申告内容に基づいて、評価額の計計算(減価償却)と税率(1.4~1.6%)の掛け算をします。計算根拠はあくまで、所有者からの自主申告です。(関連記事で償却資産税の節税交渉の記事があります)
固定資産税はその逆で、税務申告が不要です。市役所が勝手に税金計算をし、課税します。
計算根拠は登記簿と実物で、計算方法は不動産鑑定士の報告に基づきます。不動産鑑定士の評価が決め手なので、所有者からしたら実感がない話です。
2.周囲の成功体験談
5月といえば、納付書が届く時期であると同時に、多くの場合、1回目の納税期限です。コロナ危機ということもあり、市役所に相談する人は多いと思います。
✔︎無策でも成功した事例
ぶっちゃけ、私はこのマネごとです。ただただ、期待をもってしまします。
✔︎勉強しまくって成功した事例
固定資産税(市税)の減額交渉が成功し、不動産取得税(県税)でも過払い認定された事例です。言い方悪いですが、市役所って、結構ミスるんですね。
✔︎気づいたらゼロになっていた事例
納付書が来ないから確認したらゼロだったという事例です。羨ましい。。。
3.なぎささんの交渉ネタ
さて、周囲の事例に踊らされ、私も一歩踏み出てみました。こう見えても、前職は東証一部上場企業の財務部で固定資産を専門で見ていた立場です。償却資産税の減税を勝ち取った過去もあります。
✔︎まずは勉強 評価額は妥当なの?
償却資産税なら詳しいですが、不動産鑑定士の目線はありません。
まずは評価額の妥当性を確認しました。
国交省のH Pから不動産取引の売買実績が確認できます。このデータを使えば、その場所の平米単価が算出できます。この平米単価と納付書記載の評価額が同レベルか。これが確認点となります。
補足すると、私は土地を太陽光発電設備とセット買いしました。請求書の中では土地は広さ・地形に関わらず10万円です。消費税還付を最大限に取る策(逆に償却資産税はUP)なので、こんな金額になっています。なので、外部データを使わないと説得力がありません。
さて、金額確認すると、平米単価はこのようになります。
- 国交省より 平米単価(3,500円)*面積(1,168m2) = 4,088,000円
- 納付書より 評価額 = 9,565,920円 (税額93,746円)
あまりに違いすぎます。なので、交渉ネタ。
✔︎地目は妥当なの?
地目はなぜか納付書と登記簿で不一致になっていました。
- 納付書では 宅地
- 登記簿では 雑種地
通常雑種地の方が安いはずなので、なんだか変ですね。
ここも交渉ネタです。
✔︎レッツ交渉
では、レッツ電話です。おさらいすると、
- 納付書記載の評価額が、実勢価格(国交省H P)より高い
- 登記簿では雑種地なのに、納付書では宅地扱い
私は不動産鑑定士の評価方法まではわからないので、あくまで「教えてもらう立場」を念頭に、心のどこかで、「無策でも成功した事例」を意識していました。
で、電話をしていろいろ聞いてみると、、、
4.交渉結果とそこからの学び
結論NGでした。
✔︎交渉結果
まず、兵庫県の土地は宅地です。
30年近く前に山を切り開いで宅地造成場所で、家が今だに立っていない場所7軒分を太陽光発電に転用しました。除草効果のある土壌処理をしたので、実質もう宅地ではありません。登記簿では雑種地に地目変更をしたばかりです。
また私は10万円で買った土地ではありますが、その前のオーナーは#円で購入していたようです(国交省より)
この前提からいくと、ある程度下がるのでは、、、と思うのですが、
✔︎学び#1
土地の評価額は不動産鑑定士が実地調査したばかりで、値下がり代がない。
一般的な平米単価は91,00円だが、角地制限等で使えない場所を減額評価しており、8,190円で計算しているとのこと。
実勢価格(3,500円)との差は、今後長期的には解消されるかもしれないが、あくまで妥当な評価らしい。
→つらい😢 安値のものに実質的な高額課税やん!!!
✔︎学び#2
宅地造成された場所は、登記が変わっても未来永劫「宅地」として課税されるらしい。
→つらい😢😢 納得もいかない。「気づいたらゼロになっていた事例」とは話が逆やん!!!
宅地としての課税に関しては納得がいかないので、法律?を勉強してみます。
不動産鑑定士って、どんな人